第11回「南極の歴史」講話会 気象観測の話 (2012年12月15日)
|
★第2次南極観測の思い出
立平 良三(第2次隊・宗谷)
|
|
★南極オゾン観測の事始め
清水 正義 (第7次越冬)
|
|
★気象観測の概要と
9次、13次の気象観測
福谷 博(第9次・13次越冬)
|
|
案内資料: 当日の写真: 当日の写真: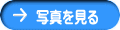
第11回目の「南極の歴史」講話会(2012年12月15日15時より、日本大学理工学部8号館831号教室)は、定常気象観測を話題として開催された。
南極での観測には、基本観測と研究観測があり、基本観測には定常観測とモニタリング観測がある。通常、南極での観測といえば研究観測が多いのだが、一方、毎日毎時、地道にデータを取り続けている観測がある。それらは気象、電離層、潮汐、地震観測などである。 これらの観測は正確な均一のデータを蓄積していくことが重要な責務である。
今回は、これら定常観測の中の気象観測にスポットを当てた。定常気象観測はこれまで気象庁がその責務を負ってきた。国内の気象観測と同じ基準で観測を実施している。歴史的に見ると今回はそのほんの一部を、2次隊の「宗谷」で参加した立平良三氏、昭和基地再開時、7次隊で参加した清水正義氏、9次隊・13次隊で参加した福谷 博氏に当時の気象観測などについて語っていただいた。
★ 第2次隊の気象観測の思い出 立平 良三(2次隊・宗谷)
56年前の1957年の秋、南極観測船「宗谷」は竹芝桟橋から南極に向けて出港した。筆者は久我雄四郎・田島成昌両先輩とともに船上気象観測の担当として乗り組んだ。越冬隊の気象担当は守田康太郎・清野善兵衛・川口貞男・矢田明の四氏だった。
ここで筆者が記すのは南極観測とはいっても南極海における船上気象観測に限られる。もっとも、第二次南極観測は、「宗谷」が南極海で海氷に閉じ込められ、越冬隊を残せなかったので、昭和基地での気象観測はない。タロとジロなどの樺太犬も昭和基地に置き去りにせざるを得なかった。
第2次観測では、船上気象観測担当者は海上保安庁の航海士として「宗谷」に乗り組んだ。このような体制は観測船が「宗谷」である間は続いた。船上気象観測は、南極海に限らず、東シナ海‾インド洋を航海中も3時間ごとに一日8回実施した。
更に、一日2回地上天気図を作成し、風や降水の予想も発表した。風は海氷の密集・離散を支配する主要因である。またヘリや航空機の運用にも気象実況および予想は重要である。
筆者は一日5回の海上気象観測、南半球各気象通報局からの気象放送の受信および天気図記入を担当し、毎日11時から翌1時までの14時間勤務だった。南極海で行動中の約三か月間休みなしの14時間勤務はかなり苦しかった。唯一の息抜きはデリンジヤー現象である。無線通信が途絶するので、気象放送受信作業から解放された。しかし、残念ながら1〜2時間程度しか続かなかった。
もちろん筆者の分担だけが過重だったわけでなく、三人で当時の測候所並みの業務をこなしていたわけである。ちなみに久我、田島の両氏は、大戦中に気象担当の海軍士官として軍艦に乗り組んでいた経歴があり、筆者も陸軍関係の学校の生徒だったことがあるので、まだそのムードが残っていたのかも知れない。さらに、命じられてもいないのに500mb 高層天気図まで作成していた。
一時、「宗谷」はこのまま海氷に閉じ込められ、船で南極越冬という事態も憂慮されたが、米国の砕氷艦「バートンアイランド号」に曳航され、ようやく氷海を脱した。その途中、曳航用の太い麻綱?が切れたことがあって大騒ぎになった。
帰路、シンガポールで偶々「バートンアイランド号」にそっくりのプラモデルを見つけ、お土産に買って帰った。箱にはEastwind class Icebreaker とあった。「バートンアイランド号」はこのclass の砕氷艦だったようだ。
★ 南極オゾン観測の事始め(7次隊の気象観測) 清水正義(7次越冬)
第7次観測隊は、昭和基地を恒久的な観測基地として再生させる第1陣であった。
基地再開後の気象観測は定常観測と研究観測に分けられ、地上の定常観測は隔測方式と自動処理による省力化、あるいは将来の自動処理化に備えて、「自動気象観測装置(MAMS)」と「自動気象印字装置(MAMP)」を導入し、高層の定常観測には周波数変化式RSⅡ―64型レーウィンゾンデを開発、軽量化した自動追跡型レーウィンゾンデ受信機D55Bを採用した。
気象研究観測はオゾン観測に重点が置かれ、先ず、オゾンモニター(地表付近のオゾン濃度測定用、ベックマン社)を購入。この反応管を参考にして新たにオゾンゾンデが開発され、KC型と命名した。
別に開発されていた滴定式のオゾンゾンデはKT型と命名し、両オゾンゾンデ他露点ゾンデと輻射ゾンデも用意した。オゾン全量を観測するドブソン型二重分光光度計の整備点検は、高層気象台に任せた。
第7次南極観測隊は、1965(S40)11月20日晴海埠頭出航。12月30日定着氷接岸(昭和基地の北50km)、31日現地夕方、基地へ1番機飛ぶ。1966(S41)年1月中、ブリザードなどの天候不良の間を縫ってヘリによる基地への輸送作業。
20日基地再開式。22日測風塔(10m)を建て、23日MAMS、MAMP関係を気象棟に搬入。新発電棟発電開始。
26日D55B受信機ラック、高層関係の記録器など搬入。28日放球棟の砕氷。29〜30日D55Bの自動追跡部設置。
2月1日9時越冬隊成立式。地上観測は00Z(現地時間03時)から観測通報。
2〜3 日気球充填室へ水素発生器搬入、6〜9日水素発生器整備。11日レーウィンゾンデ第1号飛揚。
第7次越冬の高層気象観測の特記事項:
①D55B自動追跡型レーウィンゾンデ受信機は、屋外にむき出しのまま使用。
②気球用の水素ガスはアンモニアを熱分解して、水素ガスと窒素ガスの混合のまま気球に充填。
③水素充填室兼放球棟の隅にアンモニアボンベと加熱分解炉を置いた。定常観測用のゴム気球(600g)は、この水素発生器で充填すると必要浮力を得るまで1時間近くかかり、屋根の開口部が狭いので、特殊ゾンデ用の大型気球(2kg)は、室内で40分ほど水素を入れてから屋外に出し、さらに60〜70分充填を続ける必要があった。
ドブソン型二重分光光度計の整備・観測:
2月1〜3日ドブソン小屋の屋根修理、関係品を開梱搬入。5日光学くさびとアンプをセット。6〜8日検定準備、波長検定、標準ランプ検定などを経て、8日観測開始。
オゾンモニターの整備:
2月8日オゾンモニター関係搬入。10日から種々の準備を重ねて、17〜19日反応液作り、2月下旬にオゾンモニターを設置したが種々のトラブルが続き、越冬半ばまでトラブルが続き、結局、全く手に負えなかった。
オゾンゾンデによる観測:
2月下旬に気象棟前室を特殊ゾンデ点検用に整備し、特にオゾンゾンデの反応管準備に時間がかかった。3月13日の夜、KCゾンデの反応液とカーボン電極を作ったが、同夜から10m/s以上の風が続き18日にようやくおさまった。朝から水素発生器の電源を入れ、9時水素充填開始、10時55分飛揚。受信記録を見ると大成功。
年末までにKCゾンデを45回飛揚した(内28回有効なオゾン鉛直分布取得)。KTゾンデは4〜7月に5回飛揚したが1回しか成功せず、以後KTゾンデを使用しなかった。特殊ゾンデ全体では3〜12月に75回飛揚した。
★ 定常気象観測の概要と9次、13次の気象観測 福谷 博(9、13次越冬)
基地再開以降の昭和基地の気象観測は、定常観測と研究観測に分けられた。研究観測とは短期的にテーマを決めて行う観測であり、定常観測は同一事項について定期的に継続して行う観測である。清水氏の行ったオゾン観測のように初めは研究観測で行ったが、やがて技術や精度が整って定常観測項目となっていく観測も多い。
定常気象観測の歴史的推移については、気象庁発行の「南極気象観測3 0 年史(1989.1.7刊)」およびその後を取りまとめた「南極気象観測5
0 年史(2008.12.10刊)」で詳しく報告されている。特に50年史では年表化されたものが掲載されており一目瞭然である。これらの書籍は気象庁図書館で閲覧できる。
ここでは定常観測について述べる。定常観測を歴史的時間経過からだけで見ると、技術的進歩に伴う観測測器や観測方法の変遷としか見えてこない。例えば、1次隊から6次隊では各観測項目について人手をかけて観測記録していたが、7次隊からは隔測・自動処理観測へ移行し、隔測・自動処理観測になった後はその更新・改善の歴史といった具合である。しかし、定常気象観測は、それぞれの地域の気象条件の中で人間の生存のための基礎的な観測である。気象の変動は日々の生活に密着し、気候変動は社会のあり方や生き方に係わっている。その係わり方を見極めていくために、同一精度の長期的データを得ることが肝要になってくる。
現在、定常観測と位置づけられている観測項目は、地上気象観測(気圧・気温・湿度・風向風速・全天日射量・日照時間・積雪の深さ・雲・視程・大気現象)、高層気象観測(気圧・気温・湿度・風向風速)、日射・放射量観測(上向き、下向き放射量・大気混濁度・波長別紫外線域日射量)、オゾン観測(オゾン全量・オゾン鉛直分布)である。
これらのことを下敷きにすると、この講話会の目的に合ったテーマは、各隊次の気象観測がいかなるものであったかをお話しするのが最良と考えた。
私が参加した9次隊では、7次隊がレールを敷いた隔測・自動処理観測方法や観測項目が大きく変わることがなかった。9次隊での特記事項はMAMS、MAMPの2号機への更新であった。しかし、設置して電源を入れたとたんに定電圧装置のダイオードやトランジスタが破損するなど思いもよらぬことが起こった。充分注意を払っていたが低温による障害であったようだ。高層観測関係では水素発生器の調子がすこぶる悪く、また充填するノズルが不良品であったため気球が炎上するなど大いに手こずった。また、高層気象観測の自動化を目論んで上層の風の計算に計算機(WAC)を導入した。これは記憶媒体に回転ドラムを使用したトランジスタやダイオードで構成された初期の計算機で、三角関数の計算をするだけで大きな金庫ほどの大きさがあった。これもしょっちゅう壊れて観測は手計算で補った。あるとき、全く動かなくなって直すのに三人で1ヶ月以上かかった。埃の多さやアースの不良など様々な原因が考えられたし、人為的なミスも重なった。
13次隊での特記事項は、気球の充填棟の移設である。それまでの充填棟は風を背にして建てられていたため、強くなると風が入り口側に回りこんで気球が引き出しにくくなってしまう欠点があった。このことを解消するため移設に当たっては主風向に対し建物の向きを45度程度振って設置した。このおかげで風船は充填棟から引き出しやすくなり、放球時の事故は大分減った。
定常気象観測担当者はこれまで気象庁職員が隊員として派遣されている。越冬隊員の1割〜2割を占める人数である。そのようなわけで越冬の生活面での要のとなることが多い。縁の下の力持ちとして今後も持続して欲しい。
<以上、南極OB会報 第18号から引用>
|
| |

