案内資料: 当日の写真: 当日の写真: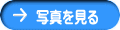
★「南極探検裏話」 沢 英武(3次夏隊,サンケイ新聞OB)
★「宗谷時代の幕開けの頃」 中村 純二(1次夏隊、2次夏隊、3次越冬隊、東大名誉教授)
第1回国際地球観測年(IGY)は1882〜83年に、第2回IGY は50年後の1932〜33年に実施され、わが国も第2回には参加した。
その後、科学の進歩は著しく、11年周期の太陽活動、従ってオーロラ出現率も、1957年頃極大になると思われたので、IGY 委員会では第3回を前回の25年後に当たる1957〜58年に行うことを決め、今回は特に南極大陸での各国の協同観測を重視することとなった。
1955年に入ると、日本学術会議内でも、是非参加したいとの声が高まり、朝日新聞も1億円を醵出して後援を申し入れてきた。
日本学術会議の茅誠司議長は、大戦終了後未だ低調だった国民の志気を昂める為にも、わが国の科学水準の高さを示す為にも、この際日本製の観測船や機器を準備して、南極観測を是非実現したいと考えていた。
白瀬中尉の南極探検に関心の深かった松村謙三文相もこれに賛同し、茲に国家事業としての南極計画案が纏まった。
同年9月ブリュッセルで開かれたIGY 委員会には、学術会議の長谷川・永田両委員が出席、以下の案を説明して、全員一致の承認を得たが、日本に割り当てられた観測地点は、東経30度付近の前人未到の厳しい大陸海岸であった。
このためわが国は、一年早く’56年に予備観測隊を送って、設営準備や本観測のための偵察を行い、’57年に本観測隊を出すことに決まった。
観測部門は気象、地磁気、極光・夜光、電離層、宇宙線、地震、地理、海洋等、設営部門は建築、機械、航空、医学、通信、食糧、装備、犬等の各学会が協力、観測船は海上保安庁に委嘱して宗谷を改装し、念のため髄伴船として東京水産大学の海鷹丸に同行して貰うことも決まった。
この間、マスコミの協力は、国民、特に小中高校生にまで大きな影響を及ぼし、寄付金なども次々に申し込まれて、事業は大いに盛り上がった。中でも朝日新聞社は援助金や濤沸湖訓練への協力、宗谷へのセスナ機の貸与等、貢献度が大きかった。
時期は相前後するが、最終的には次の組織と体制が固まった。南極地域観測統合推進本部(松村本部長)、日本学術会議内の南極特別委員会(茅委員長)、寄付金凡ての受け入れ機関は日本学術振興会となった。そして観測隊長に永田武教授、設営総括の副隊長に西堀栄三郎博士、宗谷船長に松本満次海上保安官が夫々決定した。
第1次予備観測隊の出航は11月8日と決まったが、それまでの期間は数ヶ月しかなく、特に設営部門では連日午前様となる忙しさであった。特に宗谷の砕氷能力1メートルへの改装は大変で、日本鋼管浅野ドックでの夜を日についでの関係者の奮闘には頭の下がる思いであった。宗谷のレーダーは米国製、クロノメーターはスイス製であったが、この辺りが当時の日本の限界であった。
観測隊員には観測と同時に、設営の経験や知識も要求されるので、東大、京大、北大等の山岳部OB が多く選ばれたが、観測遂行の為には、それ以外の大学や研究所も必要であり、更に各メーカーから報道、芦峅寺四人衆に至るまで、全員の尽力が必要であった。
更に宗谷や海鷹丸船員の協力や、中でもビセット時の献身的な努力も不可欠で、結局参加者全員の積極的な協力により、この大きな事業は実績を残したものであり、その後の南極観測に繋いで行くことも出来たと考えられる。宗谷時代の南極観測に取り組んだ多くの方々に改めて感謝の意を表するものである。
最後に次のスライドを上映した。
○暴風圏や氷塊に挑んだ第1次の宗谷
○第3次の際、生きていたタロとジロ。
○タロ・ジロ等とともに出かけた20日間の小型犬橇旅行(中村・平山)
○オーロラ帯直下で観測された活発なオーロラや赤いオーロラ(1959年は百数十年間で太陽活動最大の都市であった)。
<以上、南極OB会報 第15号から引用> |

